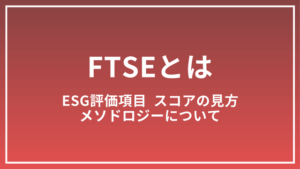目次
FTSE Blossom Japan Indexは、ESGに優れた日本企業を選定する主要なESG指数で、GPIFが採用する国内ESGベンチマークの一つです。企業にとっては、ESG評価の外部認証として活用され、構成銘柄入りは対外的な信頼性の証ともなっています。
本記事では、本指数の概要から選定基準、活用状況、構成銘柄数の傾向、最新情報などをわかりやすく解説。FTSEのESG指数への組入れを目指す企業に向けて、対応のヒントをご提供します。
FTSE Blossom Japan Indexとは?概要と特徴をわかりやすく解説
FTSE Blossom Japan Indexの基本情報と成り立ち
FTSE Blossom Japan Index(FTSEブロッサム・ジャパン・インデックス)は、ロンドン証券取引所グループ(LSEG)傘下のインデックスプロバイダーであるFTSE Russellが提供する日本株式のESG指数です。FTSE Blossomインデックス・シリーズに属し、ESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みが優れた日本企業を組入れるよう設計されています。年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が2017年7月に日本株ESG指数に連動したパッシブ運用を開始するにあたり初めて採用した国内ESG指数のひとつとして知られています。
本指数は、企業の公開情報に基づいてESG評価を行うFTSE独自のESG評価スキームを採用しています。評価は5点満点のスコアで表され、この透明性の高い評価手法により、FTSE Blossom Japan Indexは信頼性のあるESG指数として注目されてきました。
どのような目的で設計された指数か
FTSE Blossom Japan Indexが設計された目的は、ESG要素を従来の投資ベンチマークに統合し、投資家が日本の株式市場全体に近い形でESG投資を行えるようにすることです。ESGの考慮によって伝統的な時価総額加重のベンチマークから大きく乖離しないよう設計されており、市場全体に対して中立的なアプローチを採用しています。これにより大型株中心の幅広い日本株ポートフォリオにESG評価を組み込んだ形で投資でき、トラッキングエラーを抑えつつESG投資を実現することができるとされています。
ESG投資シリーズとしての位置付けと特徴
FTSE Blossom Japan Indexは、FTSE Russellが提供するグローバルなESG指数シリーズの一部として位置付けられています。世界でも有数の歴史を持つFTSE4Good Indexシリーズの評価スキームをベースとしつつ、日本市場向けに調整されたローカルESG指数であり、国内外の機関投資家から広く利用されています。
特に2017年にGPIFがESGパッシブ運用のベンチマークとして採用して以降、その存在感は大きく高まりました。GPIFが本指数を採用した背景には、ESG情報の開示促進を促すことで日本株式市場全体の情報開示の質の向上を図る狙いがあります。FTSEのESG評価は他評価機関と比較し網羅的なテーマが適用され、開示の有無を問う絶対評価の側面が大きいという特徴があるため、FTSEのESG評価で高い総合スコアを取得しFTSE Blossom Japan Indexに採用されることは、ESG情報開示に網羅的に取り組んでいることの証明になると考えられます。加えて、GPIFの要求に応える形で組入基準が明確である点も特徴です。
その他の特徴として、業種ニュートラルな構成を採用している点が挙げられます。これは組入銘柄の業種比率が、市場全体(親指数)の業種構成比率とほぼ同じになるよう調整されていることを意味します。これにより、特定業種への偏りを避けつつESG評価の高い企業群で構成されているのが特徴です。
FTSE Blossom Japan Indexの構成銘柄と仕組み
最新の構成銘柄数と構成銘柄一覧
FTSE Blossom Japan Indexの構成銘柄数は年々増加傾向にあり、企業のESG開示強化に伴って拡大しています。2025年6月の定期見直し時点では、親指数であるFTSE Japan All Cap Index(1,401社)を母集団として過去最多の406社が選定されています。GPIFが運用を開始した2017年6月時点では151銘柄でスタートしていることから、約7年で2.5倍以上の規模に拡大し、親指数の約1/3の銘柄数に迫る勢いです。また、構成銘柄のうち総合スコア4点台の企業数も大きく増加しており、2020年~2025年の5年間で約4倍となっています。
構成銘柄には幅広い業界・業種の企業が含まれており、各業界の大手企業から中堅企業までが名を連ねています。構成銘柄については総合スコアも公表されており、最新の構成銘柄一覧は以下リンクで確認できます。
FTSE Blossom Japan インデックス 構成銘柄一覧 | LSEG
FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexとの違いとAll Cap Indexとの関係
GPIFが採用するもう1つのFTSEのESG指数にはFTSE Blossom Japan Sector Relative Indexがあります。両指数とも組入れユニバース(親指数)としてFTSE Japan All Cap Indexを採用している点は共通です。FTSE Japan All Cap Indexとは、日本の大型・中型・小型株を網羅した広範な株価指数です。一方、FTSE Blossom Japan IndexとFTSE Blossom Japan Sector Relative Indexとの大きな違いは、前者は基本ルールとして総合スコア3.3以上を採用するのに対し、後者は総合スコア2.0以上かつ各セクター内の相対評価で上位45%を新規組入れ対象にする点です。
その結果、FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexでは絶対的なスコアはそれほど高くなくても、自社セクター内で相対的にスコアが高い企業が指数に採用され得るため、FTSE Blossom Japan Indexの方が組入れに必要な総合スコアが高いことが多く、より厳選された企業群になる傾向があります。
また、FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexでは低炭素経済への移行も目指しており、オペレーショナル・カーボン排出強度の実績によってはTPI Management Quality Score(以下、TPI MQスコア)の要件も適用されます。
以下表ではFTSE Blossom Japan IndexとFTSE Blossom Japan Sector Relative Indexの主な違いを整理しています。詳細は後述の銘柄選定基準の章をご参照ください。
| 項目 | FTSE Blossom Japan Index | FTSE Blossom Japan Sector Relative Index |
| 親指数(ユニバース) | FTSE Japan All Cap Index 1,401銘柄(2025年6月) | FTSE Japan All Cap Index 1,401銘柄(2025年6月) |
| 構成銘柄数 | 406銘柄(2025年6月) | 684銘柄(2025年6月) |
| 主な指数採用基準 | 新規組入れは総合スコア3.3以上(絶対評価による選抜) | 総合スコア2.0以上、かつ同セクター内での総合スコアが上位45%圏内の企業(相対評価による選抜) |
| ウェイト | 時価総額加重(インダストリーニュートラル型) | 時価総額加重(セクターニュートラル型) |
| リバランス(構成銘柄見直し) | 年2回(6月、12月) | 年2回(6月、12月) |
| GPIF運用資産額 | 1兆4,953億円(2025年3月末時点) | 1兆3,980億円(2025年3月末時点) |
| GPIF運用開始時期 | 2017年6月 | 2022年3月 |
日本企業の採用基準とランキング事情
FTSE Blossom Japan Indexに採用されるための具体的な基準は後述しますが、新規組入れのための基本ルールは総合ESGスコア3.3以上となっています。ただ、近年の指数組入れ企業の増加を受け、今後このスコアが3.3よりも高く設定される可能性も考えられます。過去にも新規組み入れに必要なスコアの基準が上がったことがあり、現状の3.3というスコア基準は2019年12月に設定されたものです。今後も構成銘柄数が増加すれば、指数の質を維持する目的で新規組入れに必要なスコア基準がさらに引き上げられる可能性も考えられます。
また、総合スコアのランキングの観点では、指数組入れ後も各社スコアを伸ばしており、同じスコアを維持する場合、日本企業におけるスコア順位は下がる傾向にあります。日本企業全体や業界におけるランキング1位を目指し総合スコア4.9を取得する企業も徐々に増加している状況です。
銘柄選定の基本ルールと基準~ESG視点の仕組み
FTSE Blossom Japan Index:選定・構成の基本ルールとは
FTSE Blossom Japan Indexの構成銘柄は、透明性の高いルールに基づいて選定されます。評価にはFTSE Russellが提供するESGスコアが活用され、基本ルールは総合ESGスコア3.3以上の企業を組入れることですが、その他複数の要件が設定されています。
総合スコアに基づく選定基準
指数の組入れユニバース(親指数)は、FTSE Japan All-Cap Index構成銘柄です。このうち、総合ESGスコアが3.3以上の企業のみが新規組入れ対象となります。
テーマスコアに基づく選定基準
構成銘柄に採用されるためには、総合スコアの他にいくつかのテーマスコアの要件を満たす必要があります。まず、高リスクエクスポージャーの適用テーマについて、新規組入れのためにはスコア2以上を獲得する必要があります。また、気候変動(ECC)テーマにおいて、「1次インパクトサブセクター」の場合はスコア3以上、「2次インパクトサブセクター」の場合はスコア2以上が求められます。
その他の基準
上記の他、深刻な不祥事が確認された企業は組入れ対象外となるほか、原子力発電に関係する企業は健康及び安全に関する指標に関して高い基準を満たす必要があります。また、J-REITsは組入れ対象外となっています。
リバランスのタイミングと継続採用の基準
指数は年2回(6月・12月)の見直し(リバランス)で構成銘柄が更新されます。
既存構成銘柄が継続採用されるためには総合スコア2.9以上を維持する必要があります。総合スコアが2.9未満に低下した場合は除外の対象となります(猶予期間:12か月)。また、高リスクエクスポージャーの適用テーマにおいてスコア1以上、気候変動(ECC)テーマにおいて「1次インパクトサブセクター」の場合はスコア3以上、「2次インパクトサブセクター」の場合はスコア2以上を取得できなかった場合、除外対象となります。そのほか、不祥事の深刻度合いが高く、対応が遅いと評価された企業も組入れられません。
構成銘柄比率(ウェイト)の考え方
構成銘柄のウェイトは時価総額比率を基本としています。ただし、業種バイアス最小化のためインダストリー別のウェイトを親指数と同等としたり、1社あたりのウェイト上限を設定したりするなど、特定のインダストリーや銘柄に過大なウェイトが配分されないよう調整がなされています。
FTSE Blossom Japan Sector Relative Index:銘柄選定における基準の違い
先述の通り、FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexの銘柄選定基準はFTSE Blossom Japan Indexと類似するものの、総合スコア3.3以上といった絶対評価ではなく各セクター内の相対評価によって採用が決まることが大きな違いです。その他以下のような要件が設定されています。
総合スコアに基づく選定基準
指数の組入れユニバース(親指数)は、FTSE Japan All-Cap Index構成銘柄です。このうち、総合ESGスコアが2.0以上の企業かつ各セクター内の相対評価で上位45%が新規組入れ対象となります。
その他の基準
上記の他、深刻な不祥事が確認された企業は組入れ対象外となるほか、オペレーショナル・カーボン排出強度(売上高に対するGHG排出量)が高い銘柄(親指数でのランキング上位10%以上)についてはTPI MQスコアが3以上である必要があります。また、J-REITsは組入れ対象外となっています。
リバランスのタイミングと継続採用の基準
指数は年2回(6月・12月)の見直し(リバランス)で構成銘柄が更新されます。
既存構成銘柄が継続採用されるためには総合スコア2.0以上かつセクター内で上位55%以内を維持する必要があります。総合スコアが2.0未満あるいはセクター内上位55%未満に下落した場合は除外の対象となります。また、オペレーショナル・カーボン排出強度が高い銘柄(上位10%)についてはTPI MQスコアが3未満となった場合、除外対象となります。そのほか、不祥事の深刻度合いが高く、対応が遅いと評価された企業も組入れられません。
構成銘柄比率(ウェイト)の考え方
FTSE Blossom Japan Index同様、構成銘柄のウェイトは時価総額比率を基本とし、業種バイアス最小化のための調整が行われています。ただし、FTSE Blossom Japan Indexはインダストリーレベルでの調整(インダストリーニュートラル)であったのに対し、本指数ではより細かなセクターレベルで調整(セクターニュートラル)となっています。
GPIFなど主要投資家と「FTSE Blossom Japan Index」の活用
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)による採用事例
FTSE Blossom Japan Indexが一躍脚光を浴びたのは、何といってもGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)による採用です。GPIFは世界最大規模の年金基金であり、その投資先指数に選ばれることは市場関係者にとって大きな意味を持ちます。GPIFは2017年7月にESG投資の一環として本指数をベンチマークに据えたパッシブ運用を開始しました。当初採用した国内ESG指数3つのうちの一つがFTSE Blossom Japan Indexであり、日本株ESG運用の柱となっています。GPIFはその後もESG投資を拡大し、2022年3月には新たにFTSE Blossom Japan Sector Relative Indexも採用しました。
GPIFがFTSE Blossom Japan Indexを採用した理由として、指数の質の高さと市場への影響力が挙げられます。GPIFは「ESG評価の透明性が高く、企業にも評価手法が分かりやすいこと」「特定業種を除外せず市場全体の底上げにつながること(ポジティブスクリーニング)」を評価して本指数シリーズを選定したとされています。一度構成銘柄に採用されると除外されない限りGPIFが長期株主となり、ウェイト配分に応じて安定的に資金調達が行える点がメリットであり、企業がESG課題に積極的に取り組むインセンティブとなっています。
ESG投資におけるベンチマーク・インデックスとしての役割
GPIF以外の国内機関投資家も、本指数をESG投資ベンチマークとして活用しています。例えば大和アセットマネジメントの「FreeETF FTSE Blossom Japan Index」、アセットマネジメントOneの「One ETF ESG」など複数の運用会社からFTSE Blossom Japan Index連動のETF(上場投資信託)が東京証券取引所に上場しています。結果として、構成銘柄となった企業の株価には一定のサポート要因になっていると考えられます。
JPXとの連携による変更点
2025年5月、FTSE Russellと日本取引所グループ(JPX)はFTSE Blossom Japan Indexシリーズ(FTSE Blossom Japan Index及びFTSE Blossom Japan Sector Relative Index)との連携を発表しました。この合意により、TOPIXの構成銘柄でない場合は両指数から除外するという基準が2025年12月のリバランスから適用されます。また指数の名称もJPXの冠を付し、それぞれFTSE JPX Blossom Japan Index及びFTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Indexに改称されます。
FTSE Blossom Japan Indexの構成銘柄になるには
FTSE Blossom Japan Indexの構成銘柄となることは、その企業が一定水準以上のESG情報開示に対応していることを示し、1つのステータスとなっています。本指数の銘柄選定基準はESGスコアの絶対評価で基準が明確であり、ベースとなるFTSEのESGスコアも評価の透明性が高いため、目標設定がしやすいという特徴があります。
イースクエアでは、FTSEの投資家向けデータベースを利用できる環境を構築しており、蓄積された評価データおよび評価手法に対する知見をもとに、企業のFTSE ESGスコア向上、FTSE Blossom Japan Index組入れのためのESG情報開示支援をご提供しています。その結果、約10年にわたり数多くの企業様のFTSE Blossom Japan Indexの新規組入れを実現してきました。現在、当社のご支援によりFTSE Blossom Japan Indexへの組入れを達成した企業様の割合は、ご支援開始から1年で75%、2年目で94%、3年目まで継続したご支援により100%となっています。今後も本指数への新規組入れを目指される企業様をご支援してまいります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
【参考】
- FTSE Blossom インデックス・シリーズ | LSEG
- 日本取引所グループとFTSE Russell、TOPIXとFTSE Blossom Japan Indexシリーズとの連携について公表 | 日本取引所グループ
- ESG・スチュワードシップ | 年金積立金管理運用独立行政法人